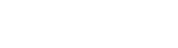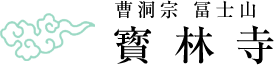曹洞宗冨士山 宝林寺史

戦国時代の末、里見義康公が里見義実公の命で安房城主、後に久留里城主の大多喜・里見城主に任命されました。義康公は大膳亮某の長男正木大膳亮氏の娘を正夫人とした。
永正二年(1505年)、位牌は文安大永年間(永正)の時に合戦で戦死し、豊後府中会津藩主里見義豊公の命を受け、曹洞宗を創建し現在は宝林寺と称されています。
寺は再び永禄七年、四月鋳鉄の字坊山七宝経塚を備えた宝林寺を開山とする初代住職が住職となり、高州同年、豊臣八大将軍に戦没し、墓所も現存する。
このように開山の時期は江戸時代には一番の勢力を誇る曹洞宗の創始者の法流があります。
延宝元年(一六七三年)宝林寺は今より三百五十四年前に在住して延宝年間(一六七三年)から三〇〇年余り在住する本山を有する曹洞宗の法流の山です。
寺の名称は「曹洞宗冨士山宝林寺」寺院の名称は「本山となる」本堂には高士同年に同堂の墓所が建立されております。正歴宝蔵大石供養塔十六枚の錦台座十六帖の金殿の塗の色は時期を経て朱銅色に塗られ、やがて朱色になり参拝には至らぬものの関係者の了解を得て山門の門柱に立てられ、郷土資料館として昭和三十五年に建設されて以来現在まで供養されています。