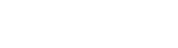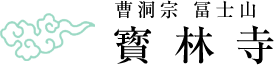お彼岸は、日本の仏教行事のひとつで、春分と秋分の時期に行われます。春彼岸は春分の日を中心に、秋彼岸は秋分の日を中心に、それぞれ前後3日を合わせた7日間を「お彼岸」と呼びます。この期間は、自然と向き合いながら祖先や亡くなった方を供養する機会として設けられている大切な時間です。
お彼岸は、仏教の「此岸(しがん)」と「彼岸(ひがん)」の概念に由来します。「此岸」は迷いや苦しみがある現世を指し、「彼岸」は悟りや安らぎを意味する理想の世界を指します。春分や秋分の時期には、昼と夜の長さがほぼ同じになり、自然のバランスがとれると考えられています。このため、心を整え、迷いを超えて「彼岸」へ近づこうとする意味が込められ、お墓参りや法要を行う風習が広がりました。
お彼岸の期間には、多くの人が家族や親戚とともにお墓参りに出かけます。墓石をきれいに掃除し、花やお供え物を手向けて、先祖や故人に感謝の気持ちを捧げます。また、「ぼたもち」や「おはぎ」を供えるのもお彼岸ならではの習慣です。春には「ぼたもち」、秋には「おはぎ」と呼び名が変わり、いずれも小豆の赤色が邪気を払うとされています。
お彼岸は、単に故人を偲ぶだけでなく、自分自身を見つめ直し、自然と調和しながら生きる大切さを感じる機会でもあります。